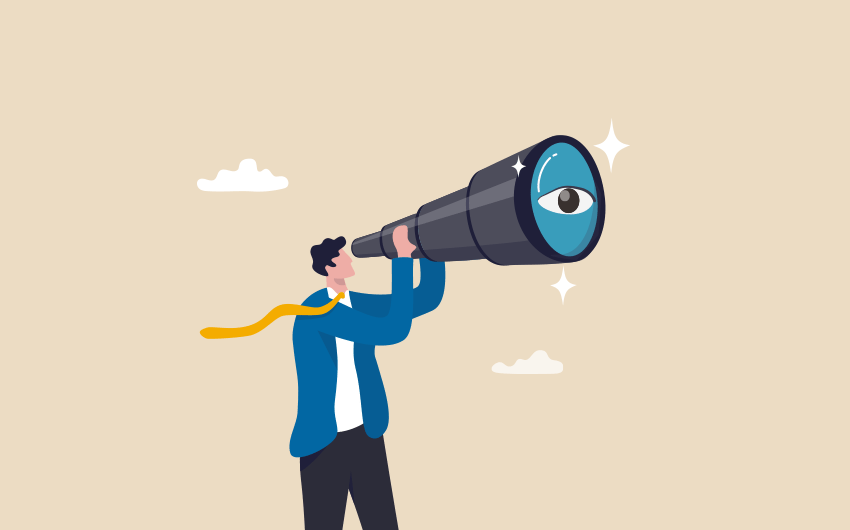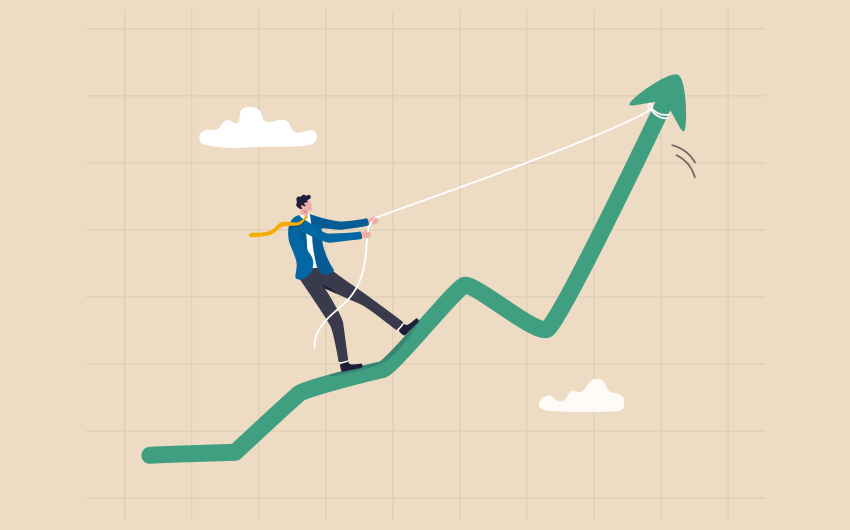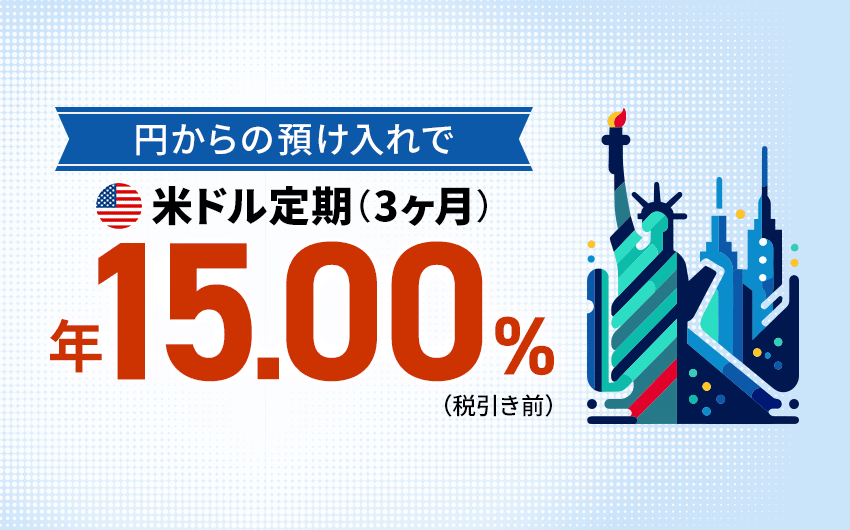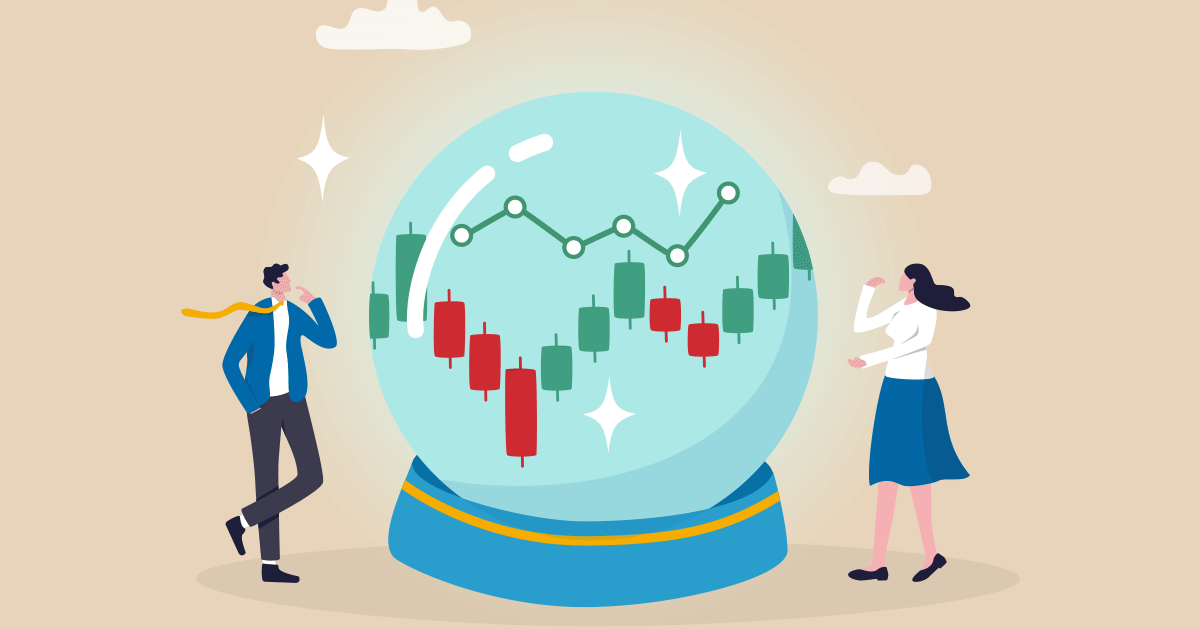
早いもので、2024年も残すところあとわずか。今年は新NISAを利用して新たに資産形成を始めた人も多いようですが、初年度の成果はいかがでしたか? 日米の代表的な株価指数である日経平均株価とダウ平均株価の推移を振り返ってみても、一時的な急落こそあったものの年間では堅調だったといえそうですから、利益が出ている人も多いかもしれませんね。
もちろん、資産形成の基本は長期投資で、短期的な成果に一喜一憂すべきではないでしょう。それでも、初年度からプラスになれば、やはりうれしいのは当然のこと。だからといって慌てて利益を確定するのではなく、ぜひ長期の目線で資産を成長させてほしいものですし、逆に現時点でマイナスだという人も、焦る必要は全くありません。ご自身の資産形成の目的を忘れることなく、じっくり投資と向き合うようにしてください。
インデックスファンドとアクティブファンドの違いとは?

まもなく、2年目の新NISAが始まります。あらたに360万円の年間投資枠が設定されますから、2024年の枠をすべて使い切った人も、再びNISAが利用できます。今年の経験を踏まえ、来年は投資額を増やしたい人、もっといろいろなタイプの商品を購入したい人、あるいは、来年こそは投資に挑戦したいと考えている人などもいるかもしれません。
そんな皆さんの商品選びに当たって、今回はアクティブファンドを選択肢に加えてみてはいかがでしょう? 最近は「投資初心者=インデックスファンドで積立投資」というイメージもあり、実際にインデックスファンドしか持っていないかたも少なくないようです。確かに商品性のわかりやすさやコストの低さなど、インデックスファンドには多くのメリットがあります。けれどもアクティブファンドにも、インデックスファンドとは異なる強みがあるのも事実です。
その最大のメリットは、ファンド・マネジャーなどの運用のプロが投資先の銘柄を厳選してくれる点にあります。インデックスファンドは日経平均株価やダウ平均株価などの指数(インデックス)との連動を目指す商品のため、景気の低迷などで株価が下落する局面では、当然、インデックスファンドも下落します。しかし、アクティブファンドであれば、そんな下落局面であっても上昇することすらありえるのです。
2025年はさらに「地政学的リスク」が高まる?
2008年のリーマン・ショック以降、世界の株式市場は基本的に右肩上がりに推移してきたといってもいいでしょう。ですから、ここ10数年ほどは株式中心のファンドに投資さえしておけば、ほとんどの人が利益を得られたという恵まれた環境でもありました。もっとも、そんな環境がいつまで続くのか、こればかりは誰にもわかりません。
ウクライナや中東の情勢は依然として不透明であり、そうした軍事的、政治的な緊張の高まりが経済に及ぼす影響を「地政学的リスク」といいますが、地政学的リスクの高い状態は今も続いています。さらに2025年1月にはトランプ氏が大統領に就任し、米中貿易摩擦の激化が予想されるなど懸念材料は少なくありません。今後の株式市場を揺るがせかねない要因に、事欠かないのは確かでしょう。
もちろん20年、30年という長期で捉え、世界全体で見れば株式市場は拡大していく可能性が高いでしょうし、それこそが長期投資のメリットです。ただし、日本1国で考えたときには、必ずしもそうとはいえないかもしれません。なぜなら、経済の拡大の大きな原動力となるのは人口であり、今後の日本は人口の減少が見込まれるため、経済全体の成長にはマイナス要素になってしまうからです。
たとえ経済全体が拡大しなくても、個々の企業のレベルで見れば長期的に成長する企業もあるのは間違いありません。そこで思い出してほしいのが、アクティブファンドのメリットです。優れた企業を選んで投資するのがアクティブファンドであり、そうした企業を見極められるかが、ファンド・マネジャーの腕の見せ所でもあります。日本株式への投資にこそアクティブファンドの強みが発揮されやすいともいえ、例えば海外株式への投資はインデックスファンドで、日本株式への投資は一部をアクティブファンドにするといった選択もありうるのではないでしょうか。
長期投資がしやすい点もアクティブファンドのメリット
ただし、一口にアクティブファンドといってもインデックスファンドよりも手数料が高いファンドが多く、運用成績がインデックスファンドを下回るファンドが存在するのも事実ですから、その見極めが重要になります。優れたアクティブファンドを選択するためには、あくまで過去の実績ではあるものの、まずはこれまでの運用成績をしっかりチェックしておくこと。さらに目論見書や運用報告書などを見れば、そのファンドがどのようなプロセスで銘柄を絞り込んでいくのかという運用方針に加え、ファンド・マネジャーのコメントや運用哲学なども公表されている場合があります。そうした考え方に共感できるかどうかも大切なポイントです。
加えて、運用方針が明確にされていることは、長期投資のしやすさにもつながります。前述の通りインデックスファンドは指数との連動を目指すファンドで、指数は数字にすぎませんから、思いを込めたり共感したりする対象には適していないかもしれません。ですから、運用成績が悪化すると、その時点で投資をやめてしまう。あるいは「やれやれ売り」といって、基準価額がマイナスからプラスに転じた時点で売却するといった行動を取りやすくなる面もあるでしょう。
その点、アクティブファンドで、しかもその運用方針に共感しているのであれば、一時的に損失が出たとしても投資を続けやすいはず。しかもその共感が単に「儲けたい」だけではなく、企業を「応援したい」という気持ちに発展すれば、より長期の目線で投資を継続できるのではないでしょうか。

これはアクティブファンドとインデックスファンドのどちらかがよくて、どちらかが悪いという話ではありません。それぞれにメリットとデメリットがあるだけです。その特徴をしっかり理解したうえで、上手に使い分けるようにすれば、資産形成の手段の幅が広がるばかりか、投資の面白さをもっと実感できるようになるかもしれませんね。