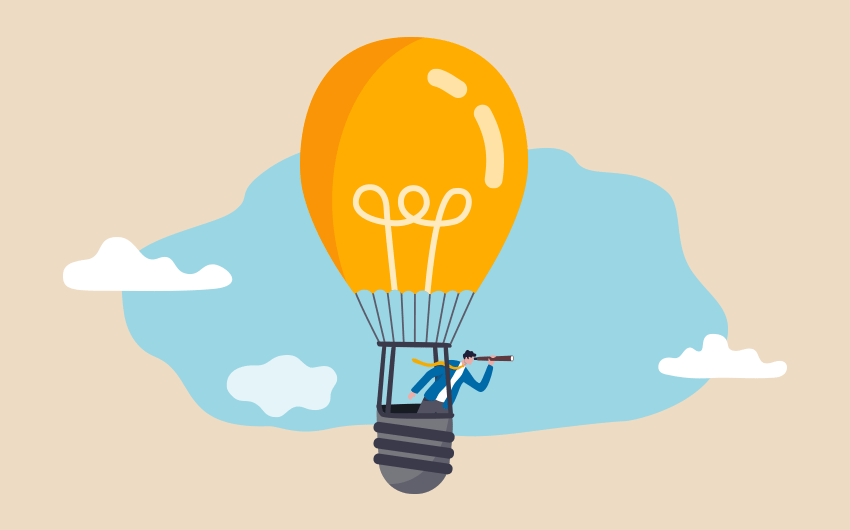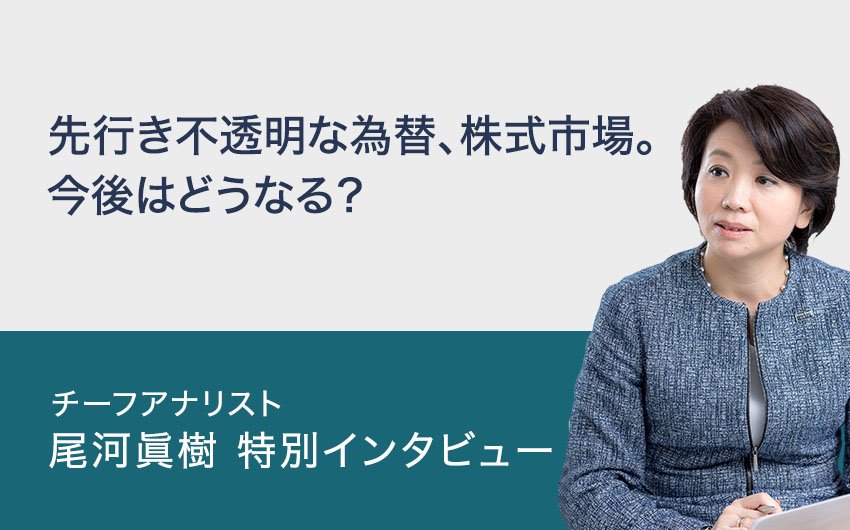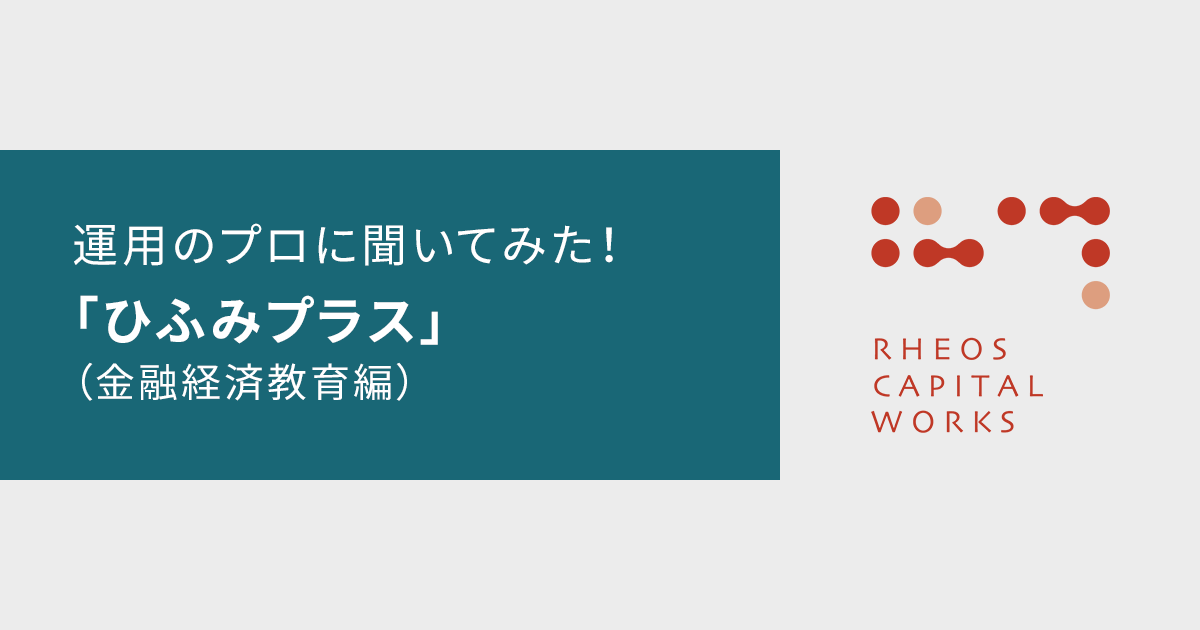
レオス・キャピタルワークス
代表取締役社長
藤野 英人さん
レオス・キャピタルワークス
営業推進本部 副本部長 兼 レオス営業部長
仲岡 由麗江さん
最近は金融リテラシーの重要性がさまざまなところで強調されるようになってきました。「資産運用立国」を掲げる政府も、2024年4月に金融経済教育推進機構(J-FLEC)を設立するなど、金融リテラシーを高めるためのさまざまな取り組みをスタートさせています。
「ひふみプラス」や「ひふみワールド+」などの人気の投資信託を設定・運用しているレオス・キャピタルワークスでも、早くから金融経済教育に力を入れてきました。その一環として、2024年11月に金融経済教育を専門とする新会社、フィナップを立ち上げたことも話題になっています。同社が金融経済教育に注力する狙いはどこにあり、実際にどんなことを実践しているのか。代表取締役社長を務める藤野英人さんと、営業推進本部副本部長の仲岡由麗江さんにうかがいました。
(参考ファンド)
ひふみプラス
ひふみワールド+
コンビニのグミの棚から子どもたちに気づきを与える
前回のインタビューでは、CIOの交代をはじめとする運用体制の変更、さらには「ひふみプラス」の足元の運用状況や今後の見通しなどについてうかがいました。今回は、貴社が早くから注力されてきた金融経済教育についてお聞かせください。
藤野 当社ではさまざまな形で金融経済教育を実践してきましたが、例えば「お金のまなびば!」というYouTubeチャンネルがあって、現在は60万人ほどのかたに登録していただいています。これは金融のエンタメ化、つまりは金融そのものを楽しいと思ってもらい、投資に対する敷居を低くすることを目的としています。しかも、単に見て終わりではなく、実際に資産運用を始めてもらえるような工夫もしていて、その成果を数字でしっかり示せることも大切だと考えています。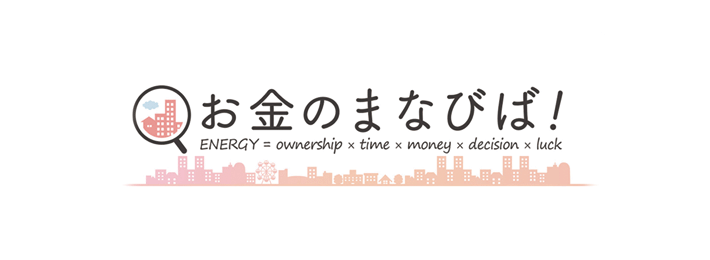 また、「ひふみ金融経済教育ラボ」という部署横断の組織を通じて、小学生から大人まで、さまざまな層を対象とした数多くの教育プログラムも用意しています。中でも好評なのが小学生を対象とする「投資家体験ワークショップ」で、詳しい内容は当社のCGOから説明させていただきます(笑)。
また、「ひふみ金融経済教育ラボ」という部署横断の組織を通じて、小学生から大人まで、さまざまな層を対象とした数多くの教育プログラムも用意しています。中でも好評なのが小学生を対象とする「投資家体験ワークショップ」で、詳しい内容は当社のCGOから説明させていただきます(笑)。
仲岡 CGOというのは藤野に命名されたチーフ・グミ・オフィサーのことですが(笑)、主に小学生向けに実施している「投資家体験ワークショップ」にはグミを題材にしたプログラムがあります。具体的には、ワークショップの場でコンビニのグミの棚を再現し、どんな位置にどんな商品があり、それがどこの会社で、デザインはどうなのか、食べ比べたりもしながら、子どもたちに気づいた点を挙げてもらいます。そのうえで、自由な発想で子どもたち同士が議論し、例えば気に入ったグミがあればなぜなのか、理由まで掘り下げていくのです。それが成長する企業を選ぶヒントになっているということに、気づいてもらうわけですね。

実はこのプログラムを始めるきっかけになったのは、当社のアナリストが実際にコンビニでグミの調査をしていたことでした。その際にどんな手法、考え方で調査を行ったのか、それで見いだされることは何か、などを社内でヒアリングしてお子さんたちにもお話しています。そうすることで、次にコンビニのグミの棚を見る時には子どもたちの目線が変わってくると思うのです。以前あったものがなくなっていて、どこの会社のものが増えたといったように、変化に気づく目が育っていくことを期待しています。最終的には、そうした日々の生活、行動も投資につながっていて、投資は特別なものではなく、身近なものだと実感してもらうためのワークショップなのです。
まさにコンビニのグミの棚から、経済が見えてくるわけですね。
仲岡 日常生活の中から社会の変化に気づくことで、会社を見る目が養われていくと考えています。それは投資だけではなく、将来、就職する会社を選ぶ際にも役立ったりしますから、親御さんも喜んでくれて、おかげさまで人気のプログラムになっています。そんなこともあって、私がいつもグミを持ち歩いているため、藤野からCGOを拝命しました(笑)。

藤野 重要なのは「見る力」だと私は思っています。この「見る力」を養うのは体験であり、逆に体験していないものは見えません。どういうことかと言えば、例えば私が若いころ、アナリストとして調査を担当した水道の蛇口を作っている会社がありました。その社長さんにお会いし、水道の蛇口の競争力やブランド価値などについて何時間も話していると、それまで見えていなかった水道の蛇口が見えるようになってきたんです。つまり、皆さんも毎日、水道の蛇口を見てはいるでしょうが、本当は何も見えていない。それは蛇口について考えたことがないからなんですね。
なるほど、確かに先ほどのコンビニのグミの棚にしても、これまで何度も見てはいるものの、グミについて考えたことはありません。それは見ていないのと同じだというわけですね。
藤野 そうなんです。グミについて考えるという体験を経ることで、グミが本当に見えるようになってきます。しかも、グミが見えることで、他の棚も見えるようになってくる。経験が増え、情報量が増えることで、見えるものが増えていくのです。この「見る力」はアナリストに欠かせないものですし、ビジネスにおいても非常に重要な能力だと言えるでしょう。ですから、子どもたちにとって先ほどのプログラムは、まさにそうした能力を養うための初めての体験になるはずです。
「仕事をすることは所属すること」という日本の仕事観
2024年11月には金融経済教育を専門とする新会社、フィナップを設立されました。今後の金融経済教育は、このフィナップに集約させていく予定なのでしょうか。
藤野 いえ、それはありません。同じ金融経済教育といっても、役割は全く違います。もちろん、連携はしますしシナジーもあるのでしょうが、フィナップではあくまでビジネスとしての金融経済教育を実践していきます。この4月からは、実際に有料のプログラムをオンラインでスタートさせていきます。
これまで日本には、体系的な金融経済教育を提供しているところがほとんどありませんでした。それが結果として、投資詐欺が横行する一因になったと私は考えています。確かに、YouTubeなどには数多くの無料のコンテンツがあり、中には優れたものもありますが、ほとんどがバラバラの知識で体系的になっていません。だからこそ、体系的な金融経済教育が必要であり、しかもそのベースとなる経済学も含めてしっかり教育していかなければならないと考えたわけで、それを担うのがフィナップです。

米国では約8割の州で経済学が義務教育になっていますが、日本では大学で経済学を専攻した人以外は、ほとんど経済学を勉強していません。そのため、小学校6年生でも40代以上の大人でも、経済の知識はほとんど変わらないとすら言えるでしょう。日本は経済大国でありながら、実はまともに経済を教えてこなかった国でもあるのです。
そうした教育の欠如が、「失われた30年」を招いてしまった原因の1つなのかもしれませんね。
藤野 特に日本では、仕事をすることが、イコール「所属すること」だと考えられてきました。どこかの組織に所属し、その指示に素直に従っていれば、月1回、いわば「我慢料」として給料をもらえる。極端に言えば、それが日本の仕事観だったのです。
けれども本来、仕事というのは所属することではなく、お客さまが求めるモノやサービスを提供し、それを売って資金を回収することです。その定義がしっかりなされない限り、本来の意味での金融も理解できませんし、起業という文化も根付きません。それは日本の根深い問題であり、その意識を変えていかないと、日本の経済は良くならないと私は考えています。けれども、経営者はもちろん、政治家や官僚もまさに所属してきた人で、しかもその中で勝ち残ってきた人たちがほとんどですから、なかなかその考え方から抜けられません。
そういえば、いわゆる一流企業に勤めていたような人でも、コロッと投資詐欺に引っかかったりするケースが少なくないのも、それが一因なのでしょうか。
藤野 そうですね。ですから、退職後にそば打ちに目覚めてお店を開くようなケースもよくあるものの、その多くが失敗してしまう。それも、これまで「所属」しかしてこなかったからなんですね。
それに対して米国では、例えば「レモネードスタンド」と呼ばれるレモネードの路面販売が子どものお小遣い稼ぎとしてよく行われています。通りを歩いている人にどうやったら喜んでもらえるのか、価格や立地も考えたうえでしっかりお金を回収するという体験をしている。それが仕事観を養い、まさに一番の金融教育にもなっているわけです。仕事とは所属することだという考え方を払拭させるのも、当社の金融経済教育の大きな目標のひとつであり、私自身の使命だとも捉えています。
そうした仕事観を養えば、企業を見る目も変化するはずですし、投資に対する考え方も変わってくるのでしょう。それでも、最近は日本でも資産運用への関心が急速に高まっているのは確かですが、最後に、なかなか第一歩を踏み出せないという人に向けてアドバイスをいただけますか。
藤野 まずは小さく始め、長く続けるということが資産運用では最も大切です。つまり、ゼロか100かではなく、とりあえず1からでいい。今は1,000円からでも投資信託が購入できますが、それでも投資家は投資家であり、最初の一歩こそが重要なのです。私たちの金融経済教育にしても、その第一歩をなるべく踏み出しやすくするためのものでもあるわけです。
冒頭でも話されていた通り、金融経済教育を通して「金融・経済は楽しい」と思えるようになることが後押しになるわけですね。本日はありがとうございました。
インタビュー・文:金融エディター 菊地 敏明
投資信託に係るリスク・費用 (レオス・キャピタルワークス株式会社のホームページへリンクします)
レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会